|
好き、と告げられたのは、カラリと乾いた7月だった。 何でもないいつも通りの会話の延長線上に、ぽつんと置かれたその言葉を理解して、即座に、悪い、と呟いていた。 その時は年下の彼女がいた。格別に好きというわけでもなかったが、好みの顔立ちだったし頭も良かったので、退屈しないと思って付き合っていたのだった。 の言葉も予想外だったが、それ以上にこんなことなら付き合っているんじゃなかった――なんてことを思う自分に驚きを隠せなかった。俺にとっては気の許せる友人で、冗談を言い合ったり他愛もない悪戯で反応を楽しんだりしているのが、一番正しいあり方だと思いこんでいたから。 自覚がなかっただけで、ずいぶん前から彼女は十分に特別だった。 そう知ってから、落ち着かない不安と焦燥に心が揺れている。 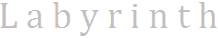
「あ、がいる」 「え?」 隣を歩いていたリーマスが、ふと指を指した。 見ると、ハッフルパフの女子二人組が廊下の端で立ち話をしている。その内の一人は、確かにだった。 「……そうだな」 「あ、図書室寄る?」 彼女らに遭遇するまでに廊下を折れると、図書室へのルートに入る。リーマスは何気ない風に尋ねてはいるが、気を遣っているのだとすぐに分かった。 「……ああ、寄るか」 「僕、レポートの資料借りなきゃ。リリーもいたらいいんだけど」 「相変わらず仲いいな、お前ら」 「いいでしょ。羨ましい?」 「別に。苦手だから」 リリーの魅力が分からないなんて、とリーマスはいつものように肩をすくめた。 角に沿って曲がりながら、ちらりとの方を見やった時、思いがけず彼女と目が合った。しかしパチと瞬きをして、すぐに視線は逸らされた。 その瞬間に、心臓がきゅっと震えて、脈々と波打つ全身の血の温度が、すみずみまで変わっていくのが分かった。でもそれがどんな感情ゆえなのかは、正直に言うと自分でもよく分からない。 恐怖のような、失望のような、安堵のような。彼女に対して抱く気持ちは一見雑多に見えて、実際はすべての感情が集まった塊のようなものだった。 軽い足取りで前を行くリーマスの後ろ髪をぼんやりと見つめながら、自分の不甲斐なさに嘆息した。 リーマスには事情を話していない。 それでも何となく察するところがあるのか、今のように一緒に行動している時には、道を変えたり話を逸らしたりしてくれている。そんな配慮を感じるたび、良い友人を持ったという思いと、友人に気を遣わせているという思いが交差して、スッキリしない。 いっそのこと、今から全て告げてみようか。そう考えついたものの、話したところでまた気を遣わせてしまうことは明らかなので、すぐに諦めなければならなかった。 (まあ、あと数年で卒業だ) 卒業してしまえば、故郷に帰ると言っていたとは二度と会うことはないだろう。今はそんな心の余裕はないけれど、全部忘れたら恋人の一人でもつくって、今までのもやもやした気持ちに完璧に蓋をすればいい。大概のことは、時間が解決してくれるだろう。 図書室に入れば、紙とインクの匂いに包まれて心が凪いだ。 特に深く考えずリーマスの後ろに着いて歩いていると、閲覧室の一席にリリーが座っているのを発見した。 「リリー。こんばんは」 リリーは素早く顔を上げて、リーマスに向かってにっこり微笑んだ。 笑顔だけなら、可愛らしいと言えなくもない。そんな、ジェームズに言えば「この罰あたりが!」という言葉と共に靴下(それもたっぷり一日分履かれた)が飛んできそうなことを考えていると、彼女はこちらにも気付いて驚いた顔をした。 「シリウスじゃない。一体どういう風の吹きまわし?」 「俺がいて何か不都合が?」 「あなたがいるとあの糞眼鏡野郎まで来そうで不吉だから、なるべく顔を見せないで欲しいものね。……あら、リーマスったらひどい顔色ねえ。ちゃんと食べてるの?」 もう慣れっこになっているとはいえ、この態度の変わりようは何だ、と憤慨したくなる。リリーはリーマスに対しては極端に声が甘くなる。そんなにも気が合うのだろうか。 「あのなあ……」 「シリウス、落ち着いて。リリーに、教授からの伝言を預かってて、探してたんだ。Aクラスに移動なんだってさ」 「まあ、嬉しい。私あの授業すごく好きなのよね」 「僕も一緒にAに移動になったんだ。よろしく」 「確か、とアンナもいたはずだわ。実験は彼女たちの班に混ぜてもらいましょう」 そういえば、リリーとは同じ教授に気に入られているとかで、よく話をしているところを見かける。ジェームズなどは「見ろよあれ! 同じ寮の僕とはあんなに楽しそうに話をしないのに」と、二人を恨めしげに見ながらよく嘆いている。そのたびに俺は、彼女らが同じ女性同士だという事実以上に、お前の日頃の行動に原因があるんだろうと突っ込みを入れたい衝動を抑えている。 全く予期していなかったわけではないが、リリーの口から出た「」という名前に居心地の悪さを覚えて、俺はふらりとその場を離れ、書架の合間を歩き出した。 ふわふわと浮いている本にぶつからないように、タイミング良く頭を引いたり避けたりするのは、ホグワーツに一年以上住んだ者ならお手のものだ。 「よ、っと」 少しスピードを出して角を曲がってきた本にぶつかりそうになり、持ち前の反射神経で避けると、本はおじぎをするようにクイクイと縦に揺れてから、横を通り過ぎて行った。その本を見送って再び前を向くと、さっき本が飛び出してきた角から見知った顔が現れた。 「……よう」 「……こんにちは」 「さっきも見たけど。廊下のところで」 「私も見たよ。リリーと話してたのを」 の表情はいつもと変わらず、ほんのりと微笑んでいる。彼女がどんな意図をもって言葉を選んでいるのか、分からない。それが分からないことに、必要以上に不安になる自分自身に驚いている。 「あー……今、時間あるか?」 「え?」 「ちょっと話したいことがある」 は何も言わずに着いてきた。 思いつくまま、ほとんど勢いだけで誘ったのだが、こうもすんなりと着いてこられては、この後の展開が怖い。これが嵐の前の静けさなら、この後の俺に待っているのはこっ酷い拒絶しかないだろう。 歩いている間、俺は考えていた。 つい十分ほど前まで、と自分との間にあったことは全てなかったことにしようと考えていたはずだ。それなのに、のことが話に出るたび、彼女の姿を見かけるたびに、もやもやとあのよくわからない感情の塊が心を支配する。 この気持ちを、時間が簡単に解決してくれるとは到底思えなかった。よしんばお互いに何も接触のないまま卒業したとしても、胸に残るしこりと長い間格闘する自分自身の姿が目に浮かぶのだ。 それなら、いっそのこと彼女に側にいてくれるよう頼むほうがずっといい。 これは、我が身可愛さのあまり、というやつに他ならないし、リーマスが知ったら蔑むどころが絶交されそうだ。それでも、引き返すという選択肢はもう捨てていた。 彼女のことが特別だと思う。 好きだ、と断言することはできないけれど。 「この間の話なんだけどさ、あれ、なかったことにしてくれないか?」 目的地。人目につかない裏庭の一角まで辿り着いて、俺は口を開いた。 「なかったこと?」 もさすがに怪訝そうな顔をする。こういう顔を見るのも久しぶりだった。 こうなる前は、幼い子供のような悪戯を仕掛けた時の彼女の笑った顔が好きで、エスカレートしては怒られ、謝ってまた笑い合って……それを延々と繰り返していたことを思い出す。 は笑うとえくぼができる。眠っているときは、本当に幸せそうな顔をする。照れた顔――クリスマスのパーティでドレスを着たが可愛くて、思わず額にキスした時――口が変な形に歪んで、わたわた、と取り乱しているのが可愛かった。 そんな色んな彼女の顔を、今のの顔に重ねていると、彼女が痺れを切らして言った。今は苛々しているようだ。呼び出した本人がぼんやりしているのだから、無理もない。 「何をなかったことにするの?」 「俺が断ったことだよ」 「……それは……どういう?」 「に、側にいて欲しい」 そうすっぱりと言い切ってしまうと、ミントの葉を嗅いだような、爽やかな気持ちになった。迷路の出口が見えたような、そんな感じがした。 そうだ。その通りだ。 心の中で大きく頷いている俺に反して、は腕組みをしたまま、顔中に「不可解」と書いて唇を尖らせた。 「私のことが好きなの?」 「……それは、また後々確信できる時がくると思う。とりあえず今は、この不自然に離れている今の状況が嫌なんだ」 彼女はようやく、「不可解」を引っ込めた。というより、謎を謎のままで受け入れようとしている。 「シリウスって、よくわかんないわね」 「そうか?」 「まあ、とりあえずOKしておいてあげる」 言うが早いか、は踵を返した。 、と名前を呼んでみたが、振り返ってはくれない。追いかけて手を掴むと、渋々立ち止まってくれた。 「何? まだ何か用?」 「側にいるんだよな。本当に」 はきょとんとして、それから久しぶりに少し微笑んだ。 「違う寮なんだから、ずっと一緒にはいられないわよ。あと十分で寮に戻らないと」 「明日は?」 「……仕方がないから、明日だけ一緒に朝食食べてあげるわ」 「OK。おやすみ」 俺に片方の手を握られたままのは、困った子供に手を焼く母親のような顔をしている。 それがなんとなく面白くなかったので、俺はふと思いついて、少し屈みこんでにキスをしてみた。 は、あのクリスマスの夜のような顔をしてくれた。 |